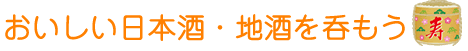弥生・大和時代
酒が米を主体として造られるようになったのは縄文時代以降、弥生時代にかけて 水稲農耕が定着した後で、西日本の九州、近畿での酒造りが起源と考えられます。 この頃は加熱した穀物を口で噛み、唾液の酵素で糖化、野生酵母によって発酵 させる「口噛み」という方法を用いていました。 酒を造ることを「醸す」といいますが、この「噛む」が語源だといわれており、 口噛みの作業を行うのは巫女に限られていました。 大和時代になると国内に広まっていった酒造りは、古事記や日本書紀、万葉集 などの文献にも見られるようになります。 また「サケ」という呼称ではなく、「キ」「ミキ」「ミワ」「クシ」など さまざまな呼ばれ方をされていました。
奈良・平安時代
奈良時代には中国で開発された麹による酒造りを、百済から帰化した須須許里 (すすこり)が伝承したと古事記に記されており、この麹は加無太知(かむたち) と呼ばれています。 これにより米麹による醸造法が普及するようになります。 律令制度が確立されると造酒司という役所が設けられ、朝廷のための酒の 醸造体制が整えられ、日本国内の酒造技術が一段と進んでいきました。 平安時代に編纂された延喜式には、米、麹、水で酒を仕込む方法、そしてお燗に 関することが記載がされています。 この時代のお酒は宗教儀礼的な要素が強く、まだ庶民の口に入ることは 多くなかったようです。
鎌倉・室町時代
鎌倉時代に入ると質素を旨とする気風は守られながらも都市化が進み、 商業が盛んになるにつれて米と同等の経済価値を持った商品としてのお酒が 流通するようになります。 朝廷の酒造組織から寺院や神社が酒を造るように替わり、京都を中心に 造り酒屋が現れだします。 室町時代初期の御酒之日記には、麹と蒸米と水を2回に分けて加える段仕込みの 方法や乳酸醗酵の応用、木炭の使用などが記されていますので、この頃には 現在の清酒造りの原型がほぼ整ったことになります。